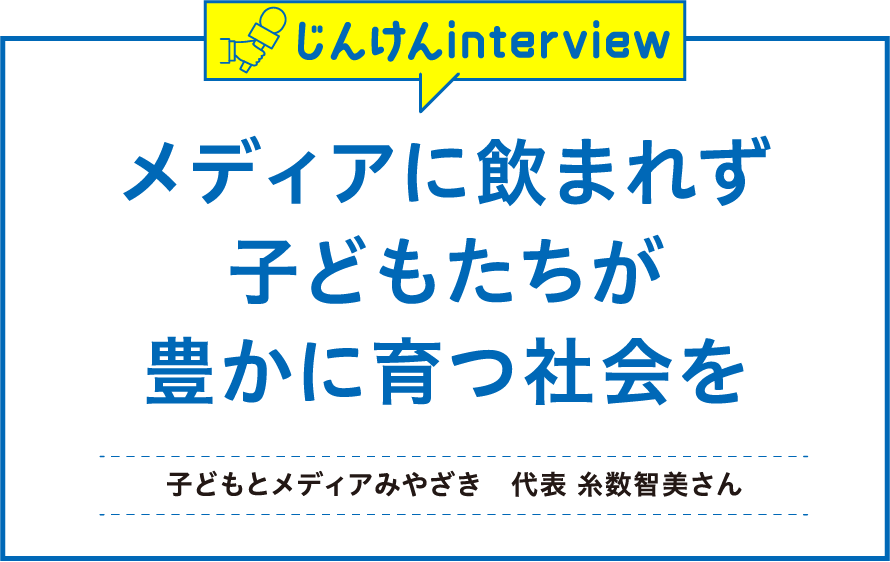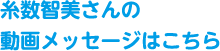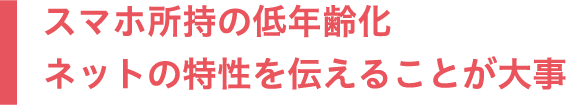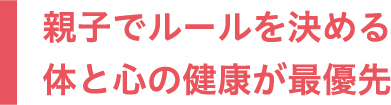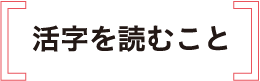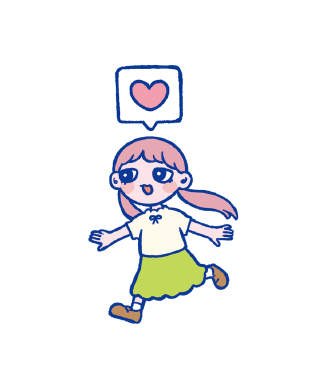2010年頃からスマートフォンが普及し始め、子育ての場にもデジタルデバイスが入り込んできました。授乳中のお母さんがスマホを見ていたり、子どもがぐずればタブレットを見せたりする。私の診療所でも以前は待合室で、親子で絵本を読む姿があったのですが、急速にスマホに取って代わられました。そんななか、2017年に「子どもとメディアみやざき」を発足させました。現在、子どもや保護者向けの講演会や研修会、学校での実態調査などを行っています。
学校のアンケートで分かってきたのが、スマホを所持している子どもの低年齢化です。小学校1年生の4人に1人、3年生の3割がスマホを持っています。小学3年生で、ネットで知り合った人と実際に会ったことがあると答えた子が約10%いるという驚きの結果もあります。幸い、犯罪やトラブルに巻き込まれたという回答はありませんでしたが。
子どもたちには、ネット上のやり取りというのは、とても情報不足になりやすいと伝えています。直接会って話すときの100分の1くらいしか相手に伝わらない。だから誤解を生みやすく、様々なトラブルの原因になると。一時の感情にまかせて、自分の言葉がどんな意味を持つのかよく吟味しないままボタンを押してしまうと、あっという間に世界中に広がります。世の中には自分と違う考え方、感じ方をする人たちがいるということを知っておくなくてはいけません。